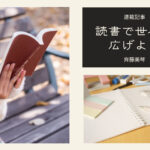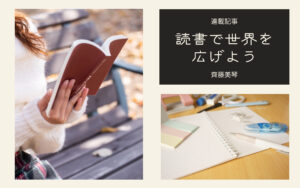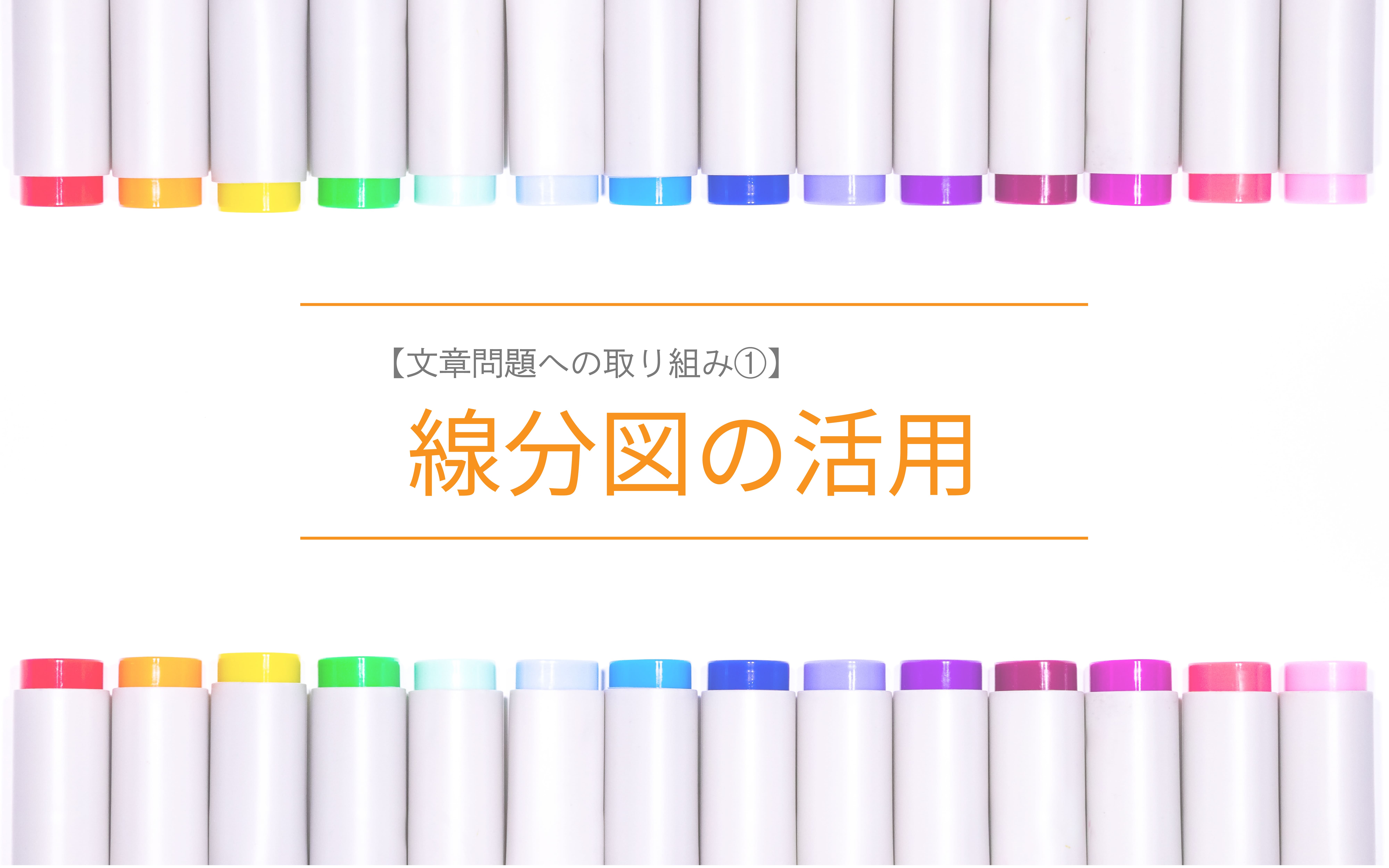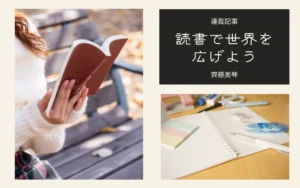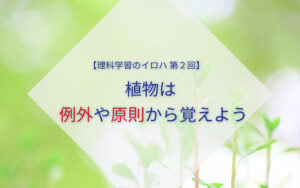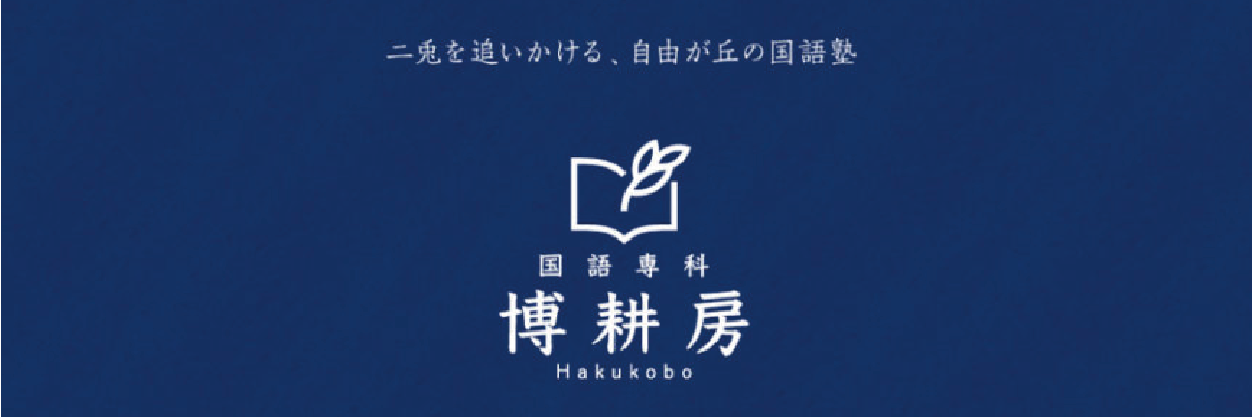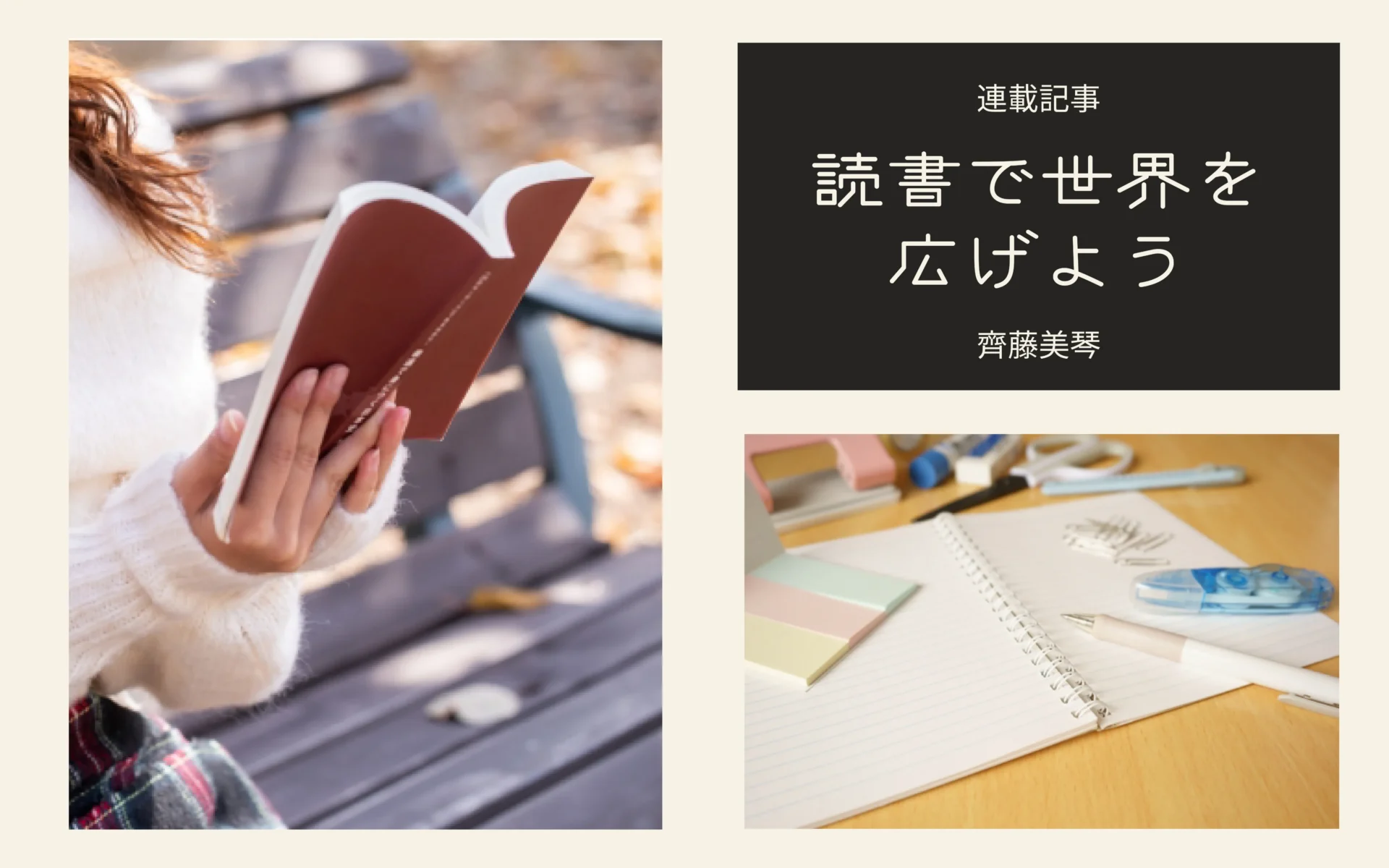
新聞社の取材チーム渾身の取材
今回取り上げるのは、岩波ジュニア新書から2024年に出版された『野生生物は「やさしさ」だけで守れるか?―命と向きあう現場から―』です。朝日新聞大阪本社「科学みらい部」の取材チームが現場に赴き、 命の問題に日々悩みながら向きあう現場の人たちを取材し、人と生きものとの共生について考えます。
「事実の報道」だけでは伝え切れない部分に踏み込んだ取材
事実を間違いなく伝えることが新聞の役目ですが、簡潔にわかりやすく伝えることが適ったとしてもその背景にどんな思いがあるか、どんな事情があったからその出来事が起こったのかはなかなか伝わりません。
筆者である3人の記者たちは、学生時代は生物学を学んできたとのこと。生きものが大好きな記者たちが、目の前の命に向き合い、事実の報道だけでは伝え切れない部分にぐっと踏み込んだ取材をしています。
事例で「現場」の今を知ることから

各章では、多岐に渡る具体的な事例を通じて問題を考察しています。例えば、市街地に出没するシカやクマの捕獲とその後の対応。
外来種のカメと在来種のカメの扱いの違いを前にしての葛藤、湾に迷い込んで死んだマッコウクジラのその後をめぐる思いなどはどちらも大阪の事例です。都市部での事例が思いのほか多いことにも驚きます。
沖縄・久米島のアオウミガメ事件
第1章「人気者が広げた波紋」では、久米島のアオウミガメ事件が取り上げられています。2023年の夏、アオウミガメが魚網に大量にかかり、地元の漁師が刺傷したと報じられた事件です。これにより「アオウミガメがかわいそうだ」と県外からの誹謗中傷が起きました。
実際に事件が起きた1年後、沖縄タイムスでは「アオウミガメ30匹の刺傷から1年 藻場の被害が続く沖縄・久米島」と題した記事が2023年7月15日10:00に配信されました。その記事では「漁師間の自主規制で再発は抑制されているものの、アオウミガメの増加により藻場が危機的状況に。漁業とウミガメ保護の両立が課題となっている」といった内容が記されています。
このような意見に対してどのように感じるでしょうか。ぜひ本書の取材を読み、物事の一面のみを見て判断してしまうことの怖さを感じてほしいと思います。
命と向き合っている現場の声に耳を傾けて
後半の2章では、保護や駆除の現場から、生きものたちの関わり合いやつながりが生み出すものに注目し、人間が生きものの命に関わり影響を及ぼす責任にも言及しています。
それぞれの地域で、野生動物との共存を目指した道を作り始めている中、事態を複雑化しているのは、個々の状況ごとに人同士で利害が対立してしまうという現実です。野生動物が実際に生息するような地域と、そうではない都市部では異なる価値観が存在することを理解した上での議論が必要になります。
異なる目線に気づき、生き物との関係性を見直すきっかけに
生態系のバランスを保つためには難しい選択ばかりが並びます。記者たちが、そのような生きもの駆除の現場などで感じるモヤモヤする気持ちを正直に記してくれていることにもほっとします。
現場で働く人々の声を聴くことで、自分の考えとは違った目線があることに気づき、人と生きものとの関係性を見つめ直すきっかけになりますね。
「かわいそう」という気持ちは大切だけど……
タイトルにあるか鍵括弧つきの「やさしさ」という言葉は、「かわいそう」という感情とつながっています。生きものの最期を前にして抱く「かわいそう」という感情を持つことは自然なこと、でも、生きものを守り、共存しようとするときにはその気持ちだけでは解決できない問題ばかりです。
「かわいそう」と思う感情は本当に動物のためになるのか。この問いに対して、こうすれば良いといった正解は最後まで見つかりません。でも、子どもたちが本書を読むことで、良いか悪いか、と白黒つけられることばかりでないことを知り、線引きの難しさ、多角的な目線で考えることの大切さを感じてくれればと思います。